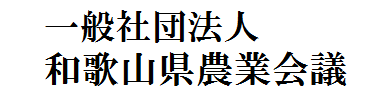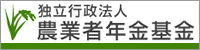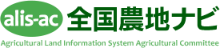認定農業者制度とは
認定農業者制度は、農業者が市町村の農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等が認定(複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定)し、これらの認定を受けた農業者に対して支援措置を講じようとするものです。
認定農業者の経営改善を後押しするため、農地・資金・税制面などの支援が受けられ、地域の信頼を得た経営が展開できます。
制度の仕組み
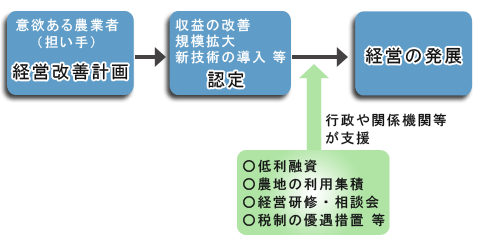
認定の対象
認定農業者制度は、効率的かつ安定的な農業経営を目指して頑張っていこうという農業者を幅広く育成していくためのものです。
したがって、農業を職業として選択していこうとする意欲のある人であれば、以下の要件を問わず認定の対象となります。
1. 性別
■男性、女性を問いません。2. 年齢
■年齢制限は設けられていません。3. 専業・兼業の別
■基本構想に定める農業経営を目指すのであれば専業・兼業は問いません。新規に就農を希望される方は、認定新規就農者と認定農業者のどちらかになることができます。
なお、認定新規就農者は認定機関の満了を迎えるまでに農業経営改善計画を作成し、認定農業者へ
移行することが推奨されています。
4. 経営規模・所得
■目標所得を目指せばよく、現在の経営規模は問いません。5. 営農類型
■土地利用型農業はもちろん、農地を所有しない畜産経営や野菜等の施設園芸なども認定の対象となります。
6. 法人経営
■農地の権利を取得して農業経営を営もうとする法人であれば、農地所有適格法人でなくとも認定の対象。集落営農も法人化すれば認定の対象となります。
夫婦や親子で認定農業者になれる?
また、家族経営協定等の取り決めで以下の事項が明確化され共同経営者となっていれば、夫婦間や
お子さん等、複数の者による農業経営改善計画の共同申請が認められ、認定農業者になることが
できます。
●農業経営の収益が申請者すべてに帰属すること
●経営の基本的事項が申請者全員の合意で決定すること
現在、単独名義で認定を受けている農業経営改善計画に経営主の配偶者や後継者等を共同経営者
として追加するときには、新たに農業経営改善計画を出し直す必要はありませんが、申請者氏名
を追加記載するよう、市長村等に計画の変更申請を行ってください。
申請窓口や手続き、認定基準等は和歌山県のホームページをご覧ください。
認定農業者が受けられる主な支援措置
認定農業者をはじめとする意欲ある農業者には、国による経営改善のための支援措置が数多く準備されています。
●経営所得安定対策
諸外国との生産条件の格差により不利がある畑作物(麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたね)を生産・販売する農業者に対して、「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」との差額分に相当する交付金を直接交付します。また、当年産の米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょの販売収入の合計が、標準的収入を下回った場合に、その格差の9割を、国からの交付金と対策加入者の積立金で補塡します。加入対象者は、認定農業者、集落営農、認定新規就農者であり、いずれも規模要件はないため、担い手は幅広く加入できます。
●制度資金
●スーパーL資金
●農業近代化資金
農業用機械・施設の整備等に必要な資金を借りたい場合に、制度資金が利用できます。
地域計画の目標地図に位置付けられた者等となった場合は、スーパーL資金や農業近代化資金の金利負担が、貸付当初5年間最大2%引き下げられます(実質無利子化)
●農地利用効率化等支援交付金
地域計画の目標地図に位置付けられた者等となった場合は、融資を活用して農業用機械等を導入する際、融資残について国庫補助を受けることができます。
青色申告をはじめると様々なメリットがあります
●農業経営基盤強化準備金制度
青色申告を行う認定農業者等が、経営所得安定対策等の交付金を準備金として積み立てた場合、その積立額を必要経費・損金算入できるとともに、それを活用して農地等を取得した場合、圧縮記帳が可能になります。
●農業者年金の保険料補助
一定の要件を満たす認定農業者等が青色申告を行った場合、保険料の国庫補助(特例付加年金の給付原資)が受けられる政策支援加入ができます。
詳しくは、市町村・農業委員会、JA、都道府県等にお問い合わせください。