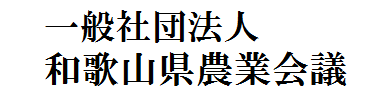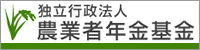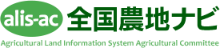農業者年金制度とは
農業者年金は、農業者の老後生活の安定を図り、農業者の確保に資することを目的とした公的年金制度です。(独)農業者年金基金では、加入者が納付した保険料を積み立て、積立金を安全・効率的に運用し、年金等を給付する事業を実施しています。
農業者年金の6つの特徴とメリット
1. 農業者なら広く加入できる
2. 積立方式・確定拠出型で少子高齢時代に強い
3. 保険料は月額2万円(35歳未満かつ政策支援加入の対象とならない方は1万円)から6万7千円の
間で自由に決められる
4. 終身年金。80歳前に亡くなられた場合は死亡一時金がある
5. 税制面の優遇措置が大きい
6. 一定の要件を満たす農業者には保険料の国庫補助(政策支援加入)がある
以上に加えて、事務経費(人件費や施設費等)は国が負担しているため、加入者が負担する必要がないことも大きな特徴です。
農業者なら広く加入できます
●農業者年金の加入要件
農業者年金は次の3つを満たす方であればどなたでも加入することができます。
1. 年間60日以上農業に従事する
2. 国民年金の第1号被保険者(国民年金の保険料納付免除者を除く)
3. 20歳以上60歳未満の方
※ さらに、年間60日以上農業に従事する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者も加入できます。
農業者としての加入要件は農業従事日数だけですので、この要件を満たせば、農業経営者はもとより、配偶者や後継者などの家族、農業従事者や農家のパートさん、自営業との兼業農家、農地の権利名義を持たない施設経営や畜産経営の農業者も加入することができます。
●加入と脱退は任意(脱退一時金はなく、将来、年金で受け取れます)
加入は任意ですが脱退も自由です。ただし、脱退された場合には脱退一時金としてではなく、それまでに加入者が支払った保険料と年金裁定までの間の運用益の分は、加入期間にかかわらず(たとえ1か月間の加入でも)、将来、年金として給付されます。
脱退された方も、加入要件を満たせばいつでも再加入できます。
積立方式・確定拠出型で少子高齢時代に強い
現行の農業者年金は、加入者の積み立てた保険料とその運用益を合せた額(年金給付原資)により将来受け取る年金額が事後的に決まる「積立方式」の「確定拠出型」を採用しています。
この「積立方式・確定拠出型」の財政方式は、保険料を支払っている方の数や年金を受給している方の数が変化しても、その影響を受けない財政的に安定した制度ですので、少子高齢時代でも安心できる制度です。
保険料の額は自由に決められます(通常加入の場合)
●通常加入の保険料はいつでも見直し可能
通常加入の保険料は、月額2万円(35歳未満かつ政策支援加入の対象とならない方は1万円)から6万7千円までの間で選べ、千円単位で自由に選択ができ、加入後でもいつでも見直すことができます。
このため、経営や生活にゆとりがない時は少ない保険料を選択し、多少ゆとりができた時は多い保険料を選択して将来に備えるといった、農業経営の状況や老後設計に合せて、保険料の額を選ぶことができる弾力性のある制度です。
終身年金。80歳前に亡くなられた場合は死亡一時金がある
●一生涯、年金を受け取れます
加入者全員が受け取る「農業者老齢年金」は、加入者が支払った保険料とその運用益を基礎として、裁定された年金額を裁定後(65~75歳)から終身(生涯)受け取ることができます。
これにより、何歳まで生きるか誰も予測できない老後生活において、ずっと一定の収入が確保できます(自己都合により60歳から繰り上げ受給することもできます)。
iDeCoや生命保険会社の年金保険等は有期であることが多く、それらに比べて大きなメリットがあります。
●80歳前に亡くなられても死亡一時金が受け取れます
仮に80歳前に亡くなられた場合は、死亡した翌月から80歳到達月までに受け取れる予定であった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が「死亡一時金」として遺族に支給されます。
税制面の優遇措置が大きい
税制面でも民間の個人年金保険とは大きく異なり、さまざまな優遇措置があります。
1. 支払った保険料が全額社会保険料控除
その年に支払った同一生計である家族分を含めた農業者年金の保険料の全額が、所得税・住民税・復興特別所得税の「社会保険料控除」の対象になります(所得税法第74条)。2. 年金資産の運用益も非課税
一般の預貯金等の利子には約20%の税金がかかりますが、農業者年金の運用益は非課税ですので、その分、年金原資が多くなります。3. 受け取る年金も公的年金等控除の対象
農業者年金として受け取った年金は、税制上、公的年金等控除の対象となり、65歳以上の方であれば、公的年金等の合計額が110万円(※)までは全額非課税となります。※ 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合
4. 死亡一時金は非課税
被保険者または受給権者が死亡した場合に遺族に支給される死亡一時金は非課税となっています。保険料支払いによる節税効果(所得税・個人住民税・復興特別所得税)の目安
|
税 率 (課税対象所得) |
加入者の支払った保険料別の年間節税額 | ||
| 月額1万円 (年額12万円)の場合 |
月額2万円 (年額24万円)の場合 |
月額6万7千円 (年額80万4千円)の場合 |
|
| 15.1% (195万円以下) |
1万8千円 | 3万6千円 | 12万1千円 |
| 20.2% (195万円超 330万円以下) |
2万4千円 | 4万8千円 | 16万2千円 |
| 30.4% (330万円超 695万円以下) |
3万6千円 | 7万3千円 | 24万4千円 |
一定の要件を満たす農業者には保険料の国庫補助(政策支援加入)
一定の要件を満たす農業者に対して、保険料の国庫補助(特例付加年金の給付原資)が受けられる政策支援加入があります。
●政策支援加入の要件
保険料の国庫補助は、次の3つの要件を満たす方は、月額2万円(固定)のうち1万円から4千円の国庫補助を受けることができます。
1. 60歳までに保険料納付期間等(カラ期間含む)が20年以上見込まれる(39歳までに加入)
2. 農業所得(配偶者、後継者の場合は支払いを受けた給料等)が900万円以下
3. 認定農業者で青色申告者などの、次の「保険料の国庫補助対象者と補助額」の表の必要な要件に
該当する
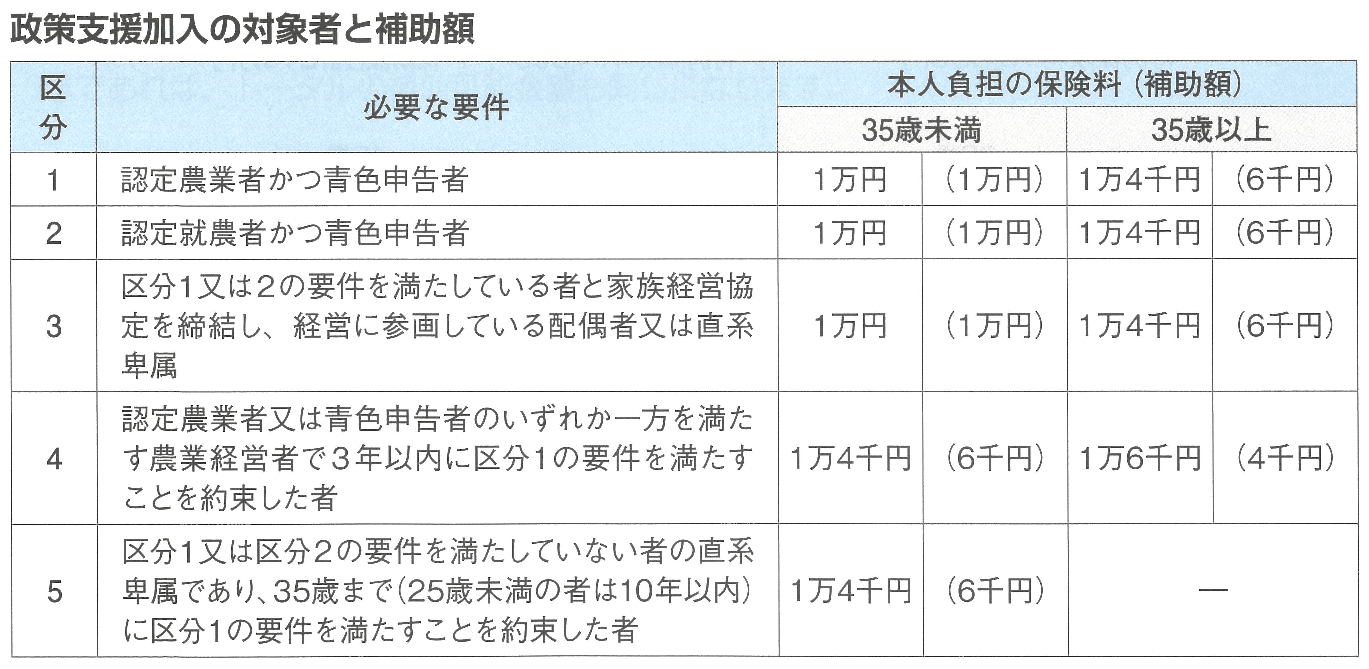
※ 35歳未満で加入した者は、35歳から自動的に35歳以上の額に変更されます。
※ 区分1~5のそれぞれの要件に該当しなくなった場合、他の区分(国庫補助額が減額になる
ことがあります)または通常の保険料への変更が必要です。
※ 保険料の国庫補助が受けられる期間は、ア)35歳未満であれば要件を満たしているすべての
期間、イ)35歳以上であれば10年以内とされ、通算して最長20年となっています。
●政策支援部分の年金(特例付加年金)の受給について
将来、自分が負担した保険料とその運用益による年金「農業者老齢年金」は、無条件で65歳から75歳で受給できますが(60歳から繰り上げ請求もできます)、保険料の国庫補助とその運用益による年金「特例付加年金」は、経営継承を行わないと受給できません。
農地や農業施設の権利を持っている人は、その権利を後継者や第三者に継承(移転・設定)する必要があります。この経営継承の時期は「何歳まで」という年齢制限はなく、本人の体力や経営の都合に合わせた時期にすることができます。
実態を伴った経営継承が必要
農業所得申告等名義など、農業経営者が保有する諸名義も併せて変更する必要があります。
詳しくは(独)農業者年金基金のホームページ、もしくは特設ホームページをご覧ください。